信濃武士と百姓のくらし
「武士の騒乱と信濃」「鎌倉時代の善光寺門前」「交通と流通」の3つのテーマから構成されています。木曽義仲からはじまる源平騒乱、守護小笠原氏を追い出した大塔(おおとう)合戦、武田信玄と上杉謙信の一騎打ちで有名な川中島合戦など、中世は戦いの時代でした。そのようななかで、中世の人びとは救いを神や仏に求めました。鎌倉時代の善光寺の門前を実物大の模型で再現し、門前に集う人びとの暮らしぶりや想いに浸ることができます。
主な展示物
撮影スポット
体験
音声ガイド
-
善光寺の門前
鎌倉時代の善光寺の門前です。善光寺の一光三尊仏は三国伝来の如来として信じられ、極楽往生を願う人々の信仰を集めました。門前では定期市も開かれ、大変にぎわいました。仏像を彫っている仏師の小屋ものぞいて見てください。
-
寺庵
寺庵は僧侶の住まいです。どんなものがあるか、くつをぬいで上がってみてください。
縁の下を見ると何かありますよ。 -

見世棚
そもそもは「見世棚」と書き、「店」とは「見せる棚」を語源とします。軒端に棚を設け、草履・草鞋などのはきものや、魚・果物・野菜などの食べ物といったさまざまな品物が売られことでしょう。
-
常設展示 解説シート
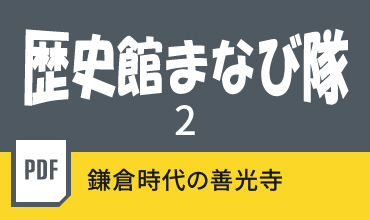
歴史館まなび隊 2
鎌倉時代の善光寺ここでは、今から700年~800年ほど前の鎌倉時代善光寺のようすを再現しています。
鎌倉時代のようすを描いた『一遍聖絵』という絵巻物をみると、当時の善光寺に集まる人びとのようすが描かれています。これを参考に再現したのがこの展示コーナーです。ダウンロード

