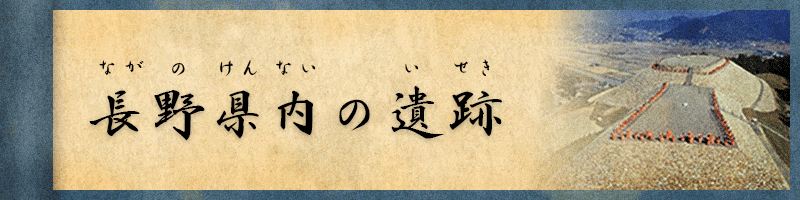
長野県内の遺跡
『長野県史考古資料編遺跡地名表』には12,665箇所の遺跡が記載されています。それらの遺跡数を時代別に示すと、旧石器時代330箇所、縄文時代7,970箇所、弥生時代2,099箇所、古墳時代884箇所、奈良・平安時代3,206箇所、中近世(鎌倉~江戸時代)約1,000箇所となっており、これらの数字の合計は15,000を超えています。これは、一つの遺跡で時代が重複する場合があるためこのような数字になっているのですが、この他にも古墳時代に3,531基にのぼる大小の古墳が築造されています。これらの数字を見てもわかるとおり、縄文時代の遺跡数の多さは、多くの研究者が「信州は縄文遺跡の宝庫」などと言い、長野県は縄文時代の最も繁栄した地域だと指摘するように、長野県の原始・古代の遺跡の特徴を示す大きな特徴となっています。
北信地方の遺跡
信濃町周辺には旧石器時代の遺跡がたくさん存在し、須坂から松代周辺には古墳時代中期以降に造られた積石塚古墳が多く存在します。その代表的な例として松代の大室古墳群があげられます。また、東信地方と境を接する善光寺平南部には森・有明山・川柳・倉科・土口といった いずれも「将軍塚」と名づけられた4~5世紀の前方後円墳があります。
東信地方の遺跡
上田周辺には弥生時代後期の遺跡が多数存在し、東山道の要衝として国府が置かれ、信濃国分寺・国分尼寺の跡が残されています。佐久周辺には縄文時代中期の遺跡が千曲川上流部や八ヶ岳山麓に多く見られ、古墳時代後期の円墳も多く残されています。
中信地方の遺跡
塩尻市柴宮遺跡からは完形の銅鐸が出土し、近畿地方からの影響が及んでいたことが推測できます。松本市には長野県最古の前方後方墳である弘法山古墳が存在し、木曽の開田高原には、旧石器時代の遺跡が多く存在します。諏訪と上田を結ぶ和田峠では黒曜石が産出し、黒曜石原産地周辺には旧石器時代の著名な遺跡が存在します。また、八ヶ岳南麓には縄文時代中期の遺跡も多数あり、「縄文時代の宝庫」を象徴するような地域となっています。
南信地方の遺跡
伊那周辺には縄文時代中期の遺跡が多数残され、河岸段丘上の大規模な集落跡も見られます。飯田周辺では弥生時代中・後期の遺跡数が圧倒的に多く、段丘上で陸耕がおこなわれていた跡が確認されています。また、古墳も善光寺平に次いで多く存在し、前方後円墳が多数あることから大和政権とのつながりも推測されています。さらに、飯田市恒川遺跡では古代地方官衙跡と推測できる遺構が発掘されています。
検索
検索の使い方
- 該当する項目に入力・チェックを入れて、検索ボタンをクリックしてください。
- フリーワードを入力していただくと、その言葉を含む記事が検索されます。
- 必ず目的の地域・市町村、時代を選択してください。選択しないと記事が検索されません。
- 地域、市町村、時代は複数選択できます。
- 複数選択をした場合には、それらすべてが含まれた検索結果となります。(アンド検索)
※長野県史刊行当時の市町村表記
※長野県史刊行当時の市町村表記
