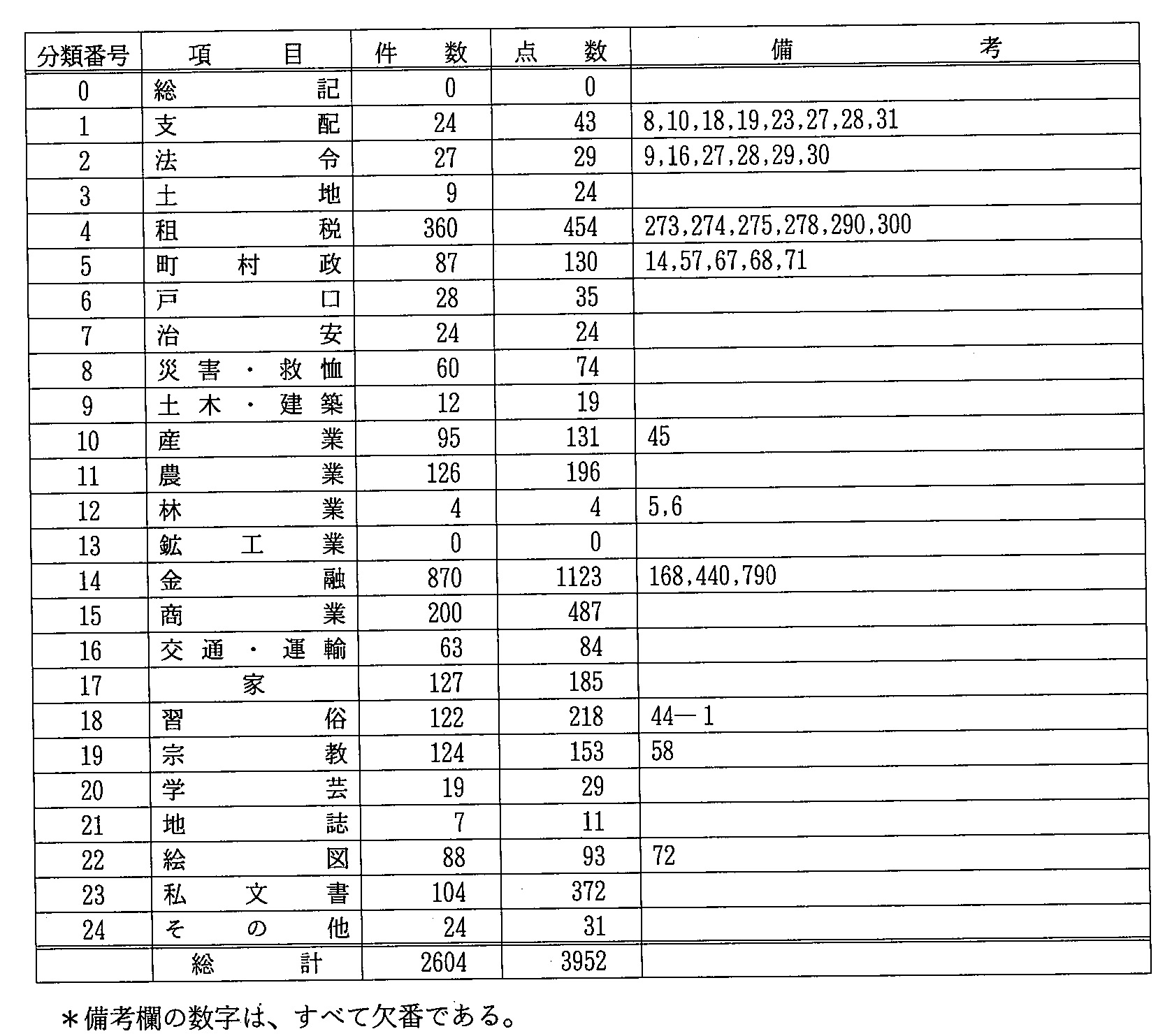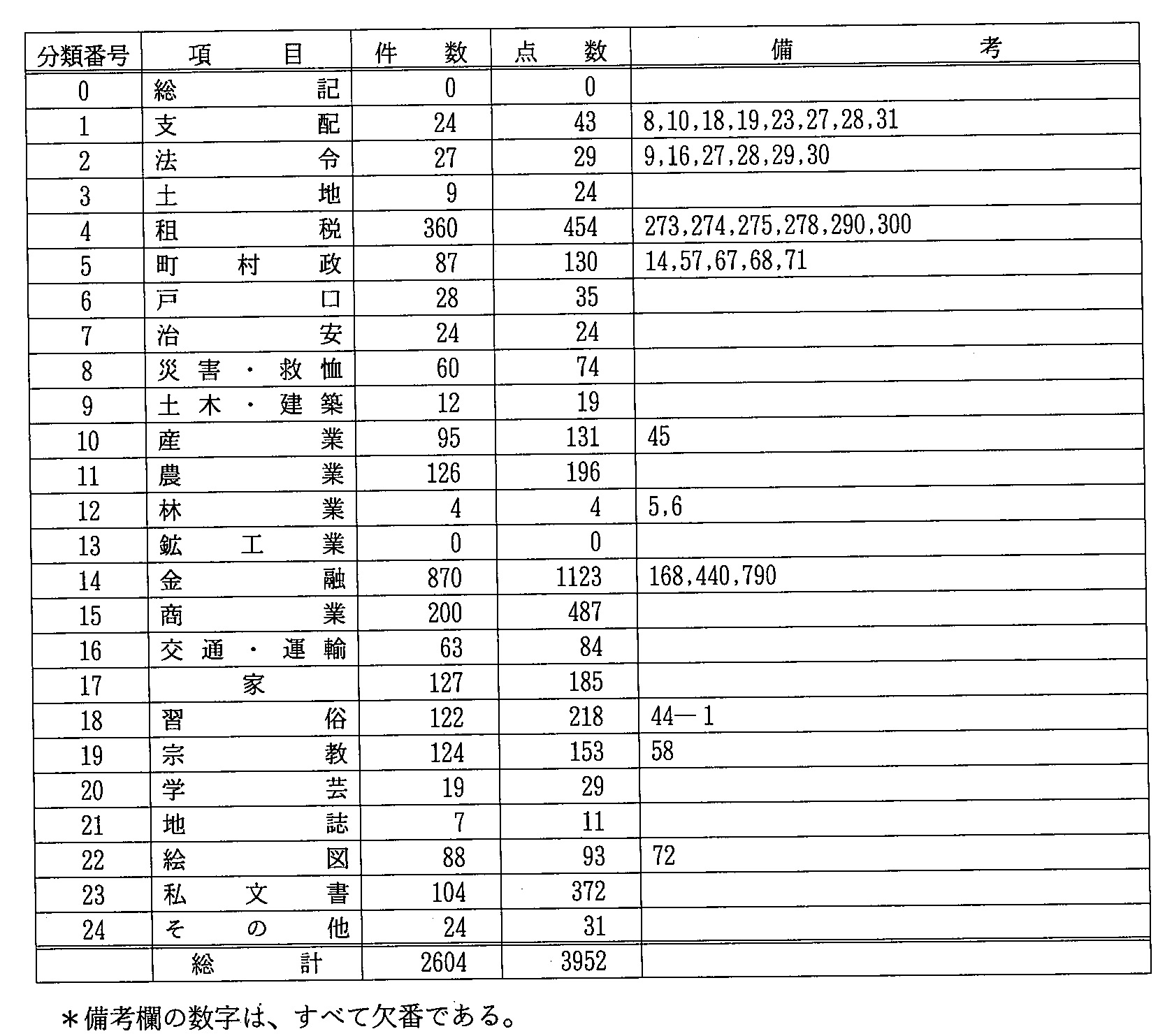
本目録に収録した久保田家文書は、県立長野図書館が昭和44(1969)年12月に、久保田八重子氏から寄贈を受けた文書である。水内郡問御所村(現長野市問御所)で名主を勤めた久保田家所蔵の文書で、年代は寛永期から明治30(1897)年代までの長きにわたる。久保田新兵衛が穀屋を営んでいたことが天保年間以降の文書にうかがえる。
問御所村は善光寺の南、北国街道の東側に位置し善光寺町・権堂村・七瀬村と接していた。公式には村であったが、江戸時代後期の文書に「町内取極」の表現がみられるように、家並みがつづく街道沿いの表通りは町場化していた。
江戸時代の初期にはしばしば領主が変わったが、元禄13(1700)年からは幕府領、寛政4(1792)年からは越後椎谷藩(藩主堀家・柏崎陣屋)領となった。椎谷藩の信州陣屋は高井郡六川(現上高井郡小布施町)にあった。同家文書のうち近世文書の多くは椎谷藩領時代のものである。寛政4年に六川陣屋へ提出した『村明細書上帳』によれば、問御所村は家数175軒、人数657人であった。また同時に作成された村絵図からは、街道沿いの家並みや土地利用のようすが知られる。村高は元禄・天保の郷帳ともに188石余で変化がみられない。
新兵衛が天保7(1836)年から書き綴った日記帳には、穀相場など経営上の記録のはかに、天保飢饉のようすや善光寺地震の被害状況がくわしく記されている。新兵衛は、善光寺地震の被災者救済等に功績があったとして、嘉永4(1851)年に大庄屋格、同5年に大庄屋見習、安政3(1856)年には大庄屋本役を仰せつかった。新兵衛と椎谷藩役人との音信文書も多い。
問御所村は明治4年椎谷県を経て長野県に属し、同9年には合併して鶴賀村の一部となった。 |